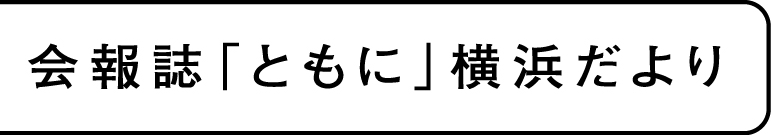19.3.4 No.46

- たとえば、多文化教員
-
私の働く大学では2018年度に朝鮮語選択者がかなり増えた。正確な統計はないし、大学ごとに外国語教育のカリキュラム、必修単位数などが異なるので一概にはいえないが、朝鮮語の選択者は日本全国で増えているだろう。ここ数年、新大久保に行くと、韓国の音楽のみならずファッションや食べ物に関心をもって訪ねてくる女子高校生、女子中学生の姿を見ることが当たり前になった。そうした先駆的な!女子中学生たちが大学に進学する時期になってきたのだから、朝鮮語選択者が増えるのも自然なことだ。第三次韓流といわれるゆえんであろう。
隣国の言葉であるにもかかわらず、それをわからないことが当然のように思われてきた時代に、終わりが来ようとしている。その点では大きな進歩だが、まだまだそれで喜んではいられない。立教大学池袋キャンパスで昨2018年12月21日に平和・コミュニティ研究機構の主催により「韓国と日本をつなぐ仕事4」という公開講演会を行なった。この間、1年に1回、文字通り「韓国と日本をつなぐ仕事」をされている方をお呼びしてお話を伺う機会を持ってきた。今回は立教大学で長く兼任講師(非常勤講師のこと)を務めておられ、NHKの放送通訳でも活躍されてきた矢野百合子先生のお話を伺った。日韓通訳・翻訳の現場でのお仕事の厳しさと面白さについてのお話とともに、いわば日韓通訳としては第一世代ともいうべき矢野先生の歩み自体が興味深かった。
講演の後に、立教大学を卒業して通訳や翻訳などの仕事をしている卒業生たちに話をしてもらった。若い世代の語学能力はとても高い。われわれ年寄りは経験が長いだけにすぎない。韓国の民主化の現代史などでは身をもって知っているとはいえ、語学の聞く、話す能力では若い世代の方が上だろう。しかし、そうして働く場を得ている卒業生たちもいれば、そうでない場合もある。韓国とかかわりのある仕事は、正直探すのが大変だ。
そうした中で、ある卒業生は韓国とはあまりかかわりのない職場だが、韓国に関連した仕事が出てくると、任されることがあるという。「韓国と日本をつなぐ仕事」は多くはないが、講演の中で矢野先生が話されていたように、ある仕事が韓国とかかわりがないと決めないで、自分の仕事の内容を拡張していけるバイタリティを持つことが求められるにちがいない。いわば日本社会もすでに変わりつつあるのだが、それに制度やシステムがついてきていないということである。
社会が変わりつつあるのに、制度やシステムがその現実に追い付いていないという点では、学校教育ほどはなはだしいものはないのではないかと思う。今、移住者の子どもたちが日本にたくさん暮らしており、その子どもたちや先生たちを支えるシステムが切実だ。しかし、移住者を労働力としては認識しても、生身の人として、家族として認識する政治家が少ない。日本語を知らない子どもたちの教育や生活に対する支援はほとんど、自治体やボランティアまかせ。
かつて、在日コリアンの若者たちの中で、学校教育の中に正規の教員として入っていくことをめざす動きがあった。先生の中にキム先生やパク先生がいたら、子どもたちももっと自分自身に自信を持てるし、在日コリアンの教員たちも子どもたちに寄り添うことができるだろう、そう思ってのことである。だが、日本の制度教育はほんの一部にしか在日コリアンを受け入れなかったし、正規教員となると、さらに一握りだ。今、同じことが中国をはじめ、日本にいる移住者、外国人の子どもたち、青年たちについて、問われているのではないだろうか。
移住者を労働力としてしか見ない政治は、日本の労働者も大切にできない。そして、目先のことしか考えられない。日本の学校で過大な業務に忙殺されている教員たちの実情は、権利を認められない移住者の子どもたちの現実とつながっている。新しい時代の開かれた学校教育を真に築こうとすれば、移住者の子どもたちに日本語を教えながら、中国語、あるいはそれぞれのルーツにつながる言葉も教えることができて、何が大切かを教えることができる多文化教員(?)を養成することが急務ではないかと思うのである。
すでにこうした仕事を実質的に行なっている地域もあるだろう。だが、それは社会にとって必要な費用なのだと認識して、政府が現実を認め予算を付けなくてはいけない。「働き方改革」を言うのであれば、ゆとりある教員数を確保する中、多文化教員を養成しようと主張してみてはどうだろうか。