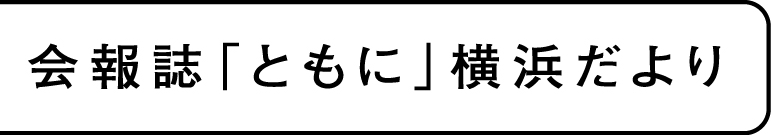22.2.24 No.64

- 「もがき」と「うごき」
-
10年ほど前、こども文化センターの職員をしていたころ、出会ったこどもがいた。小学校5年生くらいだったと記憶している。ふだんは快活で、遊びやいろいろなことをひっぱっていきながら場をつくっていくちからのある人だと感じていた。しかし、その日は様子が違っていた。放課後に来館したときから表情が平板で、ことばもあまり発さず、しばらく2Fのホールの片隅に佇んでいた。そのような姿はあまり見たことがなかった。しばらく様子をみようと階下の事務室にいたところしばらくして悲鳴のような声がホールから聞こえてきた。上がってみると、こどもはスタッフに抑えられていた。号泣しながら彼はなにかを叫んでいるのだが、はじけた想いの勢いがまさって言葉をうまく聞き取ることができない。しばらくのちに寄り添ったスタッフに聞いたところ、彼は突然叫びをあげたかと思うと近くにあったイスで窓をわろうとしたとのことだ。気持ちが少し落ち着くのに1時間ほどの時間を要した。まだ泣きじゃくる声にまじってスタッフが聞き取ったのは「こどもはおやをえらべないじゃん」という言葉だったそうだ。昨晩、父と母が言い争った末に離婚話になり、どちらに付いていくかを決めるようにせまられたのだという。それは「労働者の街」といわれる地域によくある話なのかもしれない。しかし、本人にとってはのるかそるかの決定的な時間が訪れてしまったのだと感じた。同時に「解決」のためになにができるのかを考え無力感を感じたことも覚えている。
信愛塾には、このような決定的な時間がいま、毎日のように、訪れていると聞く。全能ではなく、かといって完全に無力でもないわたしたちは、「解決」など望むべくもなく、あのこどものような存在の傍らで、そのような時間をともにしながら、「もがく」しかないのかもしれない。信愛塾のすごみは、そのような「もがき」を40年以上もの間、ずっとおこない続けているということだと感じている。そして、その「もがき」こそが、あのこどものような存在の「居場所」を一瞬この世に顕し出すのではないか、と思う。
しかし、「居場所」は「支援される側」に位置づけられる人びとにばかりでなく、「支援する側」に位置づけられる人びとにも立ち現われ続けていることと思う。
この世は「非対称的」な関係に満ちている。ある社会学者が「社会は表立って表現されることのない苦しみであふれている」と書いたことがあるが、「支援される/支援する」という「非対称的」な構造が埋め込まれた社会のなかにあって、なお、誰であれ「表立って表現されることのない苦しみ」をもっているのではないか。他者の「苦しみ」を私たちは容易に理解したり、ましてや同一視などしてはならないけれども、人間がひとりでは生きていけないことの要件は、実は、それぞれがこの「表立って表現されることのない苦しみ」を胸にいだいていることにあるのではないか。その「苦しみ」こそが、自分とは違う「苦しみ」がこの世には存在することへの理解や構想力への芽になるのではないか。それを「共感」の核と呼んでもよいように思う。
「共感」は近年あまり評判のよくない概念かもしれない。排外的なナショナリズムも一種の「共感」を持ちうるし、好き嫌い、直感的好悪という次元にのみ注目することになりかねないという批判もある。それは至極まっとうな指摘であろう。しかし、では「共感」の次元を排除したところで、人びとの苦しみに寄り添う運動はどのように紡がれるのだろうか。もちろん差別に抗うための法制度を整えることも運動の大きなモメントだが、しかしそもそもあらゆる運動には、その初発のところで、おそらくあのこどもが心のうちに抱えていたであろう「これはなんなんだ?」という問いをはらんだ微細な声やつぶやき、いや、つぶやき以前の、声にすらならない「うめき」のようなものを、誰かが聴き取り受け取った瞬間の心のゆらぎ、すなわち「共感」の次元が息づいていたのではないか。
人生を歩んでいると避けようのない苦難にみまわれ苦悩にのたうちまわるときがある。できればそのような事態はだれでも避けたいと思う。神が全能というならなぜ神はそのような苦悩を与えるのか、という問いが人類史上のあちらこちらに刻まれている。その問いへの応答を粗雑に披露するかわりに、私はいま、苦悩にさいなまれる私たちに神が贈るものについて述べようと思う。その「贈りもの」とは、神が、苦悩のうちにある私たちが気づかないうちに私たちの心に埋め込む「センサー」のようなものである。苦悩、悲しみ、痛みのなかにあるとき、自分とは違う苦悩や悲しみや痛みを感知するセンサーが私たちに贈られるのではないか。そのセンサーのスイッチがonになっているとき、私たちは、自分の経験の核に贈られた音叉のようなセンサーによって、他者の苦悩や悲しみや痛みの振動を受け止め「共振」することができるのではないか。共感とはそのようなことなのではないだろうか。40数年前、民族差別によるだれかの苦悩や悲しみや痛みを感受した、信愛塾にかかわる人びとのセンサーが、いまも生き続けてながら、もがく「運動=うごき」をつくりだしていることの深さと遥かさを想いながら、そのようなことを考えた。あのときのこどもへの遅れ馳せのひとつの応答として…。
- 振り返るとき見えてくること
-
道を歩けば、たまに周りから聞こえてくる外国人の会話、路上ではまったく違う人種、食堂に行けばよく見かける外国人従業員。私は毎日の生活でグローバル化された今日の私たちの姿を実感している。様々な背景を持つ人々の共生問題が浮き彫りになるのは、恐らく当然のことかもしれない。私はこのような時代に応える小さな実践として、信愛塾の子ども達と会うことになった。
私が子ども達に会いに行く毎週火曜日、明るい姿で信愛塾の扉を元気よく開けて入ってくる子ども達によって、信愛塾の本格的な一日が始まる。信愛塾にいる間、子ども達の大きな笑い声が聞こえてくる。勉強を終えて体育時間や自由時間が始まると、子ども達は一斉に喜びの声を上げ、帰宅時間になると、別れを惜しむ子ども達の表情が一気に暗くなるのが日常のパターンである。
子ども達の晴ればれとした姿を見ると、今まで忘れていた子ども達の居場所の重要性を改めて悟ることができる。
言葉の壁や友人との関係、勉強など日常生活における不安感を解消する居場所、母国を離れてきた異邦人としての同質感を形成する居場所、難しいことがあるたびに抜け出せる大きい木のような存在としての居場所。そのような意味として信愛塾は存在している。ここでは、子ども達が情緒的安定や付随的な助けを受けることにとどまるのではなく、しばらくの間、心理的な負担から逃れ、あるがままの自分をさらけ出し、交流し、さらに自分たちの居場所をつくりながら健康的に成長している。
私も在日外国人として、日常生活の中で、同様の苦い経験をする時がある。子ども達にも、私にも、そのような重荷があるが、毎週火曜日、信愛塾で子ども達から「チャン先生来たの?」 と、まるで友好的な友人であるかのように話しかけられると、とてもうれしくなって、心から笑い、癒される。帰り道では私の今までの居場所を振り返ってみたりする。おそらく、この子ども達との出会いを通じて、この空間は私の居場所になっていると感じる。毎週毎週いろんなことを学び、また省察する豊かな時間である。
子ども達と出会って2ヶ月余りの時間が過ぎ、今、この原稿を書いている私の心は、信愛塾のように、日本の在日外国人の子ども達の居場所がたくさん生まれてほしいという願いでいっぱいだ。子どもは未来の希望である。さらに国ごとに外国人の数が増えている世界的な傾向の下、在日の子ども達が成熟した成人に成長できるようになる社会的連帯がさらに形成されることを祈る。 信愛塾のボランティアとしての活動をしながら、私は今まで私に与えられた周りの人を疎かにしたことを反省した。このような今までの姿を改めて、新しい方向に目を向け、私は将来、居場所が必要な人々を探し、私と彼らの居場所を作るような人生を過ごしたい。 今までの信愛塾での活動を振り返ってみると、すべてが貴重な時間であった。 子ども達の未来のために今日も一所懸命に努力している信愛塾を心から応援する。
- 新横浜市長、新たな動き出てくるのか?
-
まず初めに、横浜市の国籍条項問題についてである。横浜市は1997年に職員採用の募集要項から国籍条項を原則撤廃した。つまり外国籍者も横浜市の受験が可能になった。ただ問題は「原則」撤廃である。この「原則」というのは「公権力の行使及び公の意思の形成の職に携わるためには日本国籍が必要」という1953年に出された「当然の法理」という考え方に依拠している。現在は「公務員の基本原則」と横浜市は呼び方を変えている。この「原則」に基づいて横浜市は「公権力行使業務」として市民に権利や自由を一方的に制限する業務。義務や負担を一方的に課す業務。強制力を持って執行する業務。例えば税の賦課、立ち入り調査、許認可、生活保護の決定など。「公の意思形成に参画する業務」として市行政の企画、立案、決定に関する業務。例えばラインの課長職以上、市の政策決定(予算査定や人事労務管理など)に関わる係長以上の職などを外国籍者が就けない業務として挙げている。この原則に基づくと区役所などの税金・保険年金・福祉などの多くの業務から外国籍職員が排除されてしまうのである。せっかく横浜市の職員として採用されても外国籍者であると区役所などの主要な市民サービス職場に立てないのである。これが任用制限を設けていることの問題点である。
昨年12月に横浜市国籍条項撤廃連絡会が山中竹春横浜市長宛に提出した要望書に対する回答交渉が、今年1月26日に市庁舎で持たれた。回答の中身を見ると国籍条項の完全撤廃や任用制限の撤廃要望については、「公務員の基本原則に対する国の見解を踏まえつつ、他都市の状況等、調査を行いながら、対応していきたい」としている。これでは従来と変わらないが、回答を巡る話し合いでは、〈連絡会〉「国連人種差別撤廃委員会の勧告が出ているのに考え方は変わらないのか?」〈横浜市〉「今の扱いが違憲とはならないが、他都市となぜ違うのかは探っている。例えば衛生監視員など(他都市は)撤廃しているところもあるが、横浜市とは業務整理が同じではない。同じようにできないかは検討課題。」また〈横浜市〉「業務の任用制限だが、制限する観点が厳密すぎるところがある。国の原則は無視できないが、20年も経って変えなくてよいのか?議論が必要だと思い、憲法学説を調べたりしている。来年度にかけて大元の観点を考えたい」と答えている。
常勤講師問題では〈横浜市〉「今後も国の動向を踏まえながら、対応していきたい」という回答に、〈連絡会〉「教員の人手不足は深刻だ。こういう(常勤講師)制度だとモチベーションがなくなる。ベテランになってもリーダーになれない。本人も周りの教員も納得がいかないと感じている。『差別を許さない』という方針がある中で教育の場の中で職員が矛盾があると感じている。一刻も早くなくすべきだと」と厳しく迫った。
新市長に変わって初の要望回答交渉であったが、新たな動きが感じられる部分もあったと思われる。今や「当然の法理」は時代に合わない、撤廃の動きは確実に広がっている。