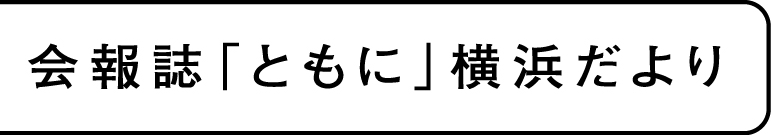22.9.22 No.67
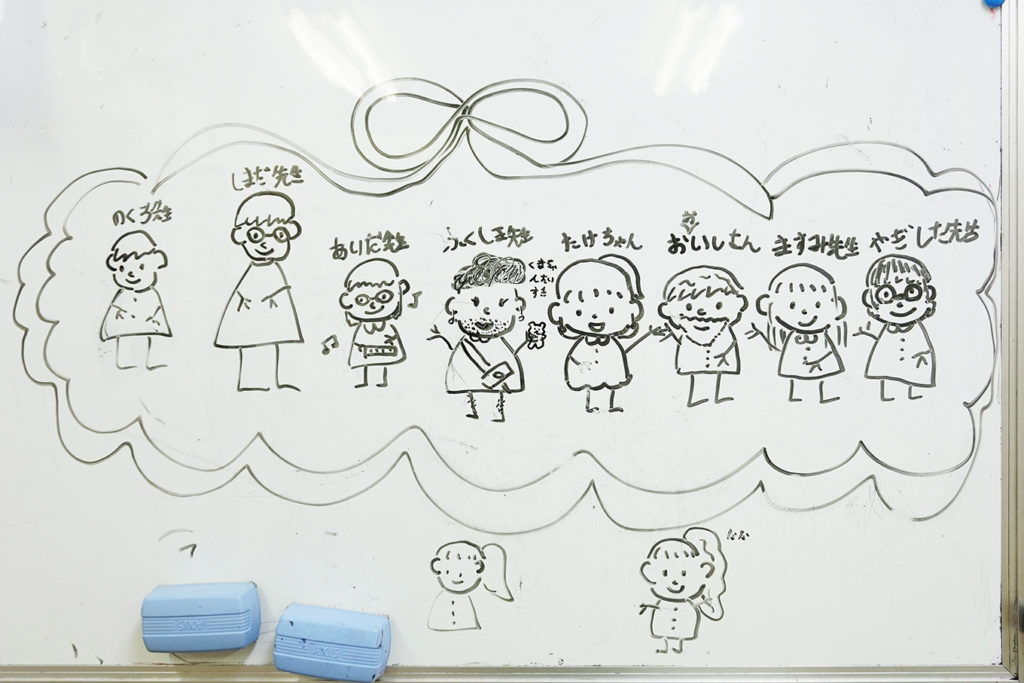
- 獐岩洞(チャンアムドン)事件のこと
-
中国吉林省延辺朝鮮族自治州。間島(カンド)の名称で知られるこの地の主要都市である龍井から車を走らせること数十分、郊外の里山で停車し、雑草の覆い茂った緩やかな丘を登っていくと大きな石碑が姿を現した。鉄柵で囲われたその石碑の正面には「獐岩洞惨案遺址」と彫られている。側面にはハングルで「1920年10月庚申年大惨案の時、日本侵略軍はここで無辜の青壮年36人を二重虐殺し、千古に容納出来ぬ〔永遠に許されぬ〕罪行を犯した」とある。
「庚申年大惨案」。これは1920年10月から11月にかけて行われた日本軍による「間島出兵」と、その時に行われた複数の民衆虐殺を指す。「獐岩洞惨案」とはそのなかの一つの事件である。
近代以降、日本は対外出兵と民衆虐殺を繰り返してきたが、日本の歴史教育の場において間島出兵について取り上げられることはまずない。韓国の歴史教科書では「間島惨変」として記述されているが、中国と日本の歴史教科書には登場しない。しかし、これは間島出兵が些末な事柄であることを意味しない。日本の対外膨張政策の連続性という観点から考えるならば、間島出兵は極めて大きな歴史的意味をもつ。
間島は中国の地にありながら、移住朝鮮人が多く暮らす地域であった。なかには独立運動を展開する勢力も含まれており、彼らを一掃する目的で行われたのが間島出兵だった。日本政府は朝鮮半島植民地支配の不安定要素を除去する目的で、中国政府の抗議を無視し、公然と出兵を行ったのである。間島はいわば対外膨張の結節点であった。
獐岩洞事件は1920年10月30日の早朝に起こった。独立運動団体が反日運動を画策しているという知らせを受け、間島に駐留していた第14師団歩兵第15聯隊の歩兵将校以下72名等が「討伐」に向かった。そして「不逞団を掃討」するためとして、村内の青壮年36名を銃殺し、遺体および家屋等を焼却したのである。冒頭で紹介した石碑の「二重虐殺」とは、焼却しきれなかった遺体を二度にわたり焼却したことを指す。
当時、この地で活動をしていたカナダ長老派宣教団所属の済昌病院院長マーチンは事件後現地に入り、住民の話をまとめ、次のように記している。
「夜明けと共に武装した日本歩兵の一隊はキリスト教村をもれなく包囲し、谷の奥の方に高く積まれたわらや穀物に放火し、村民一同に外にでるよう命じました。村民が外にでるや、父といわず子といわず目にふれるものはこれを射撃し、その半死のまま、打ち倒れるものには乾草を覆いかぶせ、識別できない程まで焼いてしまいました」(『現代史資料28』 677頁)。
虐殺された青壮年たちは独立運動に主体的にかかわる者ではなかった。事件の翌年、間島総領事代理領事が朝鮮軍参謀長に送った資料には「〔殺害された〕部落民は…犯罪を構成せざる可憐の村民なりき。若し彼等を逮捕して充分慎重に訊問したらんには刑に付せられるべき者は恐らく一人も無かりしならん」(同487頁)とある。
一般住民の虐殺と村落焼棄。なぜ日本軍はこのような蛮行に走ってしまったのか。これにはシベリア出兵が深くかかわっている。虐殺を行った第15聯隊は、シベリアからの帰還の直前に、急遽、間島に行くよう命を受けたのだった。シベリアにおいては主にハバロフスクに駐留し、1920年4月には激しい戦闘を展開している(ウラジオストクでは「四月惨変」と呼ばれる朝鮮人への武力弾圧があった)。当時、ロシア革命軍のなかには相当数の朝鮮人パルチザンが含まれており、それはハバロフスクにおいても同様であったと思われる。史料によると、「約六百より成る歩兵一大隊、乗馬若干及機関銃三銃にして約百の鮮人(ママ)隊を混ぜるが如し」との記述を確認できる(参謀本部『西伯利出兵史』第3巻 330頁)。
ただ、5月に停戦協定が結ばれて以降、戦闘はなくなった。第15聯隊に所属していたとみられる兵士が後年出版した書籍には次のようにある。
「八月九日…敵対行動の緩和と、暑気とは、遠く故国を離れ北陲の地に健闘せること稍々久しきに亙る将卒をして、漸く堕気を生ぜしめしやの感あり」、「九月二十日…敵情依然平静脾肉既に肥えたるを如何せん」(霰原桜花郎『吹雪に微笑む』300頁)。
こうした記述から、将兵は戦闘がないなかでしだいに士気が低下し、無聊をかこつ毎日を送っていたことをうかがい知ることができる。おそらく多くの兵士もまた同様の心持ちだったのではないか。そして、ようやく日本へ帰還できると思った矢先、今度は間島行きの命令が下されたのである。兵士らの心情はすさんだのであろう。間島から日本へ帰還途中の聯隊の状況について「動(やや)もすれば所謂戦時気分を以て其の態度動作放漫粗暴に流れむとするの傾向あり」と記録されており、軍紀が荒廃していたことを見て取ることができる。兵士らは鬱積した憤懣の矛先を間島の住民に向け、「討伐」によって出兵の意義を見出そうとしたのではないか。
凄惨な獐岩洞事件は、朝鮮人敵視を基層とし、そこに無為無策のまま長期化した日本軍のシベリア駐留が重なった所産だったとみることができよう。
- 私と笑顔
-
こんにちは。上智大学三年の機能創造理工学科の林健懿と申します。中国語では「リンジェンイ」と発音をします。これから私の来歴を紹介したいと思います。
私は小学二年生まで中国で過ごしていました。十歳の時、私の人生のターニングポイントが到来します。当時両親は日本に滞在し、中華料理屋を経営していましたが仕事が落ち着いたこともあり、私は日本に移り住むことになりました。日本に来るときは「嫌だ」という気持ちはなかったですがせっかく出来た友達と離れ離れになることは悲しかったです。ここから日本生活が始まります。当然ながら、来た当初は日本語をしゃべれなかったため、授業で先生が何を話しているか全くわかりませんでした。唯一の救いは教科書が漢字で書かれていたため、なんとなくの意味を理解できたことでした。そして日本語を使って同級生と意思疎通できるようになるのに8か月ほどかかりました。その間の私は、意思疎通もままならないため休み時間は自分の席にじっとして、絵をかいたり、本を読んでいました。家に帰るとき、両親はいないため私にとっての遊び相手は三歳下の弟が常でした。日本語が少し話せるようになった頃、私は鬼ごっこやドッヂボールを通して同級生と少しずつ関るようになりました。しかし、からかいと悪意の両方含め、私に対して中国のあだ名や悪口を言われることがありました。当時の私はどう対応していいかわからず暴力でやり返し、それが災いして暴力の応酬が続きました。そう言った経緯もあり、私の小学時代は殴り合いが多かったです。そんな私ですが中国の学校の勉強が過酷だったこともあり、日本に来て以降も宿題を欠かさずこなし、学校の勉強についていくことができました。もちろん、学校での国際教室や週に一回ある日本語教室の助けは大きく、日本語を基礎から教わっていただきました。このような小学時代を経験し、現在に至ります。
私と信愛塾の出会いは、高校二年生になります。きっかけは些細なことでした。SSW(スクール・ソーシャル・ワーカー)の先生から信愛塾という自分と同じような境遇の子どもたちが集まる場所があると知り、その存在に驚きました。かつての私はずっとそのような居場所を求めており、実際どのようなものか気になり訪問しました。訪問と会話を重ね、そこにいる子どもたちの助けになりたいと考え活動を初めました。
活動をする中、私が特に大切にしていきたいと考えたことがあります。それは、子どもたちの笑顔を守ることです。信愛塾に集まる子どもたちは言葉や文化、肌などつらいバックグラウンドを持っています。しかしどんな時でも彼らは笑顔を絶やしません。そんな姿を見て私はとてもまぶしいと感じました。私もかつてはよく笑っていたかもしれません。しかし成長するにつれ辛いことを多く経験し、笑顔がどういうものか分からなくなりました。しかし子どもたちを見ていると、自分も自然に笑顔になっていき、楽しいという感情をもう一度思い起こさせてくれます。子どもはよく国の宝物と表現されていますが、私はまさにそうだと感じています。そして信愛塾に集まる子どもたちは、国は違えど同じく日本の宝物であるはずです。どうか私たち信愛塾と共に先生方も子どもの笑顔を守り続けていただきたいです。