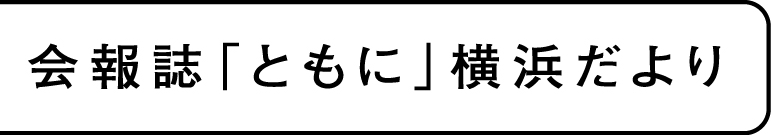23.3.16 No.70

- 在日の子として、また親として
-
私は自分の将来をあまり考えてはいなかった。頭もさほど良くないし、何につけても不器用で、世渡りも下手。金稼ぎは向いていないし、そもそも出世に興味がない。むしろ気ままに本を読んだり、楽しく酒を飲んだりしながら暮らしたいと考えていた。大学生の時も特に就職活動はせず、大学院への進学を志していた。幸か不幸か博士課程まで進学できたが、常勤の研究者になるには厳しい競争のあることを知り、「とりあえず博士論文を書いて本を出せたら本望だ。その後はどうでもいい」と思っていた。
そんな私も5年前に結婚し、今は2歳と0歳の娘がいる。親になってしまった。私は在日朝鮮人の三世として生まれ、妻とはキリスト教の現場研修で日韓の歴史をめぐる青年の旅を通して出会い、仲を深めた。5年ほどの交際を経て婚約したが、相手が日本人であったために、私の両親から1年ほど結婚に反対されていた。そして「生まれてくる子どもを在日として育ててほしい」との願いを託されて、ようやく結婚を認められたのだった。そんな私が、これから親として子どもに何をできるのだろうか。いつもそのことを考えている。
そもそも私は、在日の子どもとして、親から何を受け取ったのだろうか。私の両親は1950年代なかばに生まれた在日二世で、在日大韓基督教会の青年会を通して出会い、日本社会の中で朝鮮人として堂々と生きることを目指して結婚した。1985年には外国人登録時の指紋押捺を拒否し、裁判を行っていた。母親はその公判で次のように語っていた(『その日が来るまで―指紋押なつ拒否からの出発』、外国人登録法の改正を求める横須賀市民の会、1987年7月1日、1・12頁)。
私がまず自分自身が在日韓国人として、一人の人間として生きなければと思う。そういう私達の姿を見て、愛する子どもたちが、在日韓国・朝鮮人に対する蔑視や差別に屈することなく、豊かな心を持った人間になって欲しいのです。その存在故に、心が傷つけられることがないような強さを、身につけさせたいと思っています。
両親は当初、父の故郷である北九州で生活していた。しかし、両親が朝鮮名で生活を始めようとしたため、通名(日本名)で仕事や生活をしている父の家族と対立してしまった。その結果、私の両親は半年ほどで母の生まれ育った横須賀で暮らすことになった。父は地縁も血縁もない場所で防水工業の会社を起業し、朝鮮人の名前で仕事を受注し、働いてきた。保守的な建築業界のなかを、バブル崩壊後の不況のもとでもなお、自営業を続けてきたのである。父は当時のことをあまり語らないが、並大抵の苦労ではなかっただろう。このように、私は両親から「在日として誇りをもって生きること」を託され、また苦労のきわめて多い環境のなかで歯を食いしばって働き続けていた父の背中を見て育ったのだった。
また私の両親は機会を見つけては、私や私の姉妹を同世代の在日の子どもと出会えるようにしてくれた。私は信愛塾のキャンプに幼少期から中高生までよく参加していたし、大学生になってからは在日大韓基督教会の青年会で、同年代の友人と語らう日々を過ごした。そうした場で自分の考えをなるべく口にしていたことが、のちの研究に至る思索の基礎となった。また両親は、大学院進学後も私の研究の意義を理解して、博論が完成するまでの非常に長い日々を我慢強く見守っていてくれた。こうした中で私は在日朝鮮人として今を生きる意味を、少しずつ自分のものとしていったのだった。
しかし、私が自分なりに思索を始めた2000年代は、外国人や朝鮮人への差別感情が日本社会の中に充満していった時期でもあった。まず2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件は、「テロ対策」の名分のもとに日本政府が外国人への監視・管理を再編・強化する引き金となった。1990年代に廃止されたばかりの外国人への指紋押捺は、2007年には入国時の指紋採取という形で復活した。外国人登録法は2009年の在留管理制度改正で廃止されたが、在留カードによる在日外国人の監視・管理は形を変えて現在も続いている。
また2002年9月の日朝平壌宣言は日本と朝鮮民主主義人民共和国の国交正常化の出発点にはならず、むしろ拉致問題を口実にした「北朝鮮バッシング」の原因となった。大韓民国と日本の関係では2000年代初頭に「韓流ブーム」が起きていたが、2005年3月に島根県議会による「竹島の日」決議に対して韓国から批判がなされると、日本言論はこれを韓国の「反日ナショナリズム」によるものと批判した。1990年代には戦時下の強制連行・強制労働や日本軍「慰安婦」の被害者による戦後補償裁判が行われたが、2000年代の日本の言論はそれらの問題が「和解」に至らぬ要因を韓国の狭量な民族主義に求める文学研究者(朴裕河)を好意的に受け入れていた。さらに2007年1月には「在日特権を許さない市民の会」が発足し、在日朝鮮人の排斥を訴えるヘイトスピーチが登場した。こうして2000年代に登場した反北朝・嫌韓・排外主義の感情は、インターネットやSNSの普及も相まって、日本社会のすみずみまで定着して現在に至るのである。
21世紀を迎えてから現在までの約20年間で、日本における排外主義は相当な広がりを見せた。そのなかで私は、母方をたどれば日本にもルーツを持つ娘たちに対して、どのように「在日として生きる」ことの意味を伝えられるのだろうか。簡単に答えを出せない難問だが、少なくとも二つのことに挑戦しなければと思っている。第一には、私自身が排外主義の時代の中で、在日朝鮮人として、自分らしく、それでいて他者を踏みつけないように生きていくことである。第二には、子どもたちがどのような気持ちでいるのかをいつも気にしながら、何かに挫折した時や、差別に傷ついてしまった時に、何をおいても味方になることである。私も父や母のように、在日としての自分の生き方を子どもに示すことができるだろうか。甚だ心もとないが、とりあえず格好位はつけなければと思っている。
- 宝物(言葉のつながり)
-
この3年あまり信愛塾もコロナの影響を受けて、分散で学習支援をしています。また、学校が休校になったり、父母も仕事に打撃を受けて著しく厳しさを増してきました。ただでさえ母国を離れ、日本語の習得、生活文化の違いの中で生きていくことの困難さがある中で、マスクの強要、距離を取っての行動、黙食など、人と人との関わりが縮小されてきました。子どもたちの居場所をつくることができても、おもいっきり遊んだり心をぶつけたりする事が出来にくい環境でありました。そのため、家庭訪問をしたり、個々の学習指導をしたり物品支援や食糧支援など様々な対策がなされています。そして、公の機関の協力支援の中でも進められています。
子どもたちは自分の意志で日本にいるということより、父母の下で今の現状を受け止めています。自分はどうしたい。自分の夢は何か。時間の中で探り求めています。困難を何とも感じないような習得の速さに驚かされることがありますが、一方、つまずきを取り戻すことにも一苦労であります。昨年の夏、九九が完全に覚えられない子に小プリントを渡したまま夏休みに入りました。夏休み明けに、その子が答えを埋めたプリントを私に渡してくれました。小さなやりとりが実りますようにと思います。また、ひとりの子は、毎日信愛塾に足を運び、以前よりコミュニケーション力がとても付きました。心を打ち明けることが出来、人への手伝いも身につき、日々の積み重ねの大切さを感じます。しかし、現実に向き合うことをしないで閉じこもることもできます。答えが見つからず、らせんの中に入ってしまう危険もあります。自傷行為をする子がいたり、薬に依存する子もいると聞きます。若い時に心を開く人が一人でもいたら、相談できる人がいたらと思いますが、信愛塾はそういう子どもたちと一つのラインで繋がっています。
自然界の中での植物、木の葉でさえ、虫たちに食べられたら「今、食べられている」という信号を出しているという。それを聞いた虫は、食べている虫を追い払いに来るという。わたしたちには聞こえない言葉をもって会話をしているというのです。人と人が歩みをするうえで、自分が成功する喜びもありますが、それを共に喜び合う人がいる、共に悲しむ人が居ることも大きいと思います。生まれて父母、家族、兄弟、学友、親友、職場、社会で人間関係が広がっていきます。私も6人の子を無我夢中で育てた。自分に余裕がなく、子どもにかわいそうなことをしてしまった反省も大きい。だから、孫との時間はとても新鮮で気づくことが大きい、私の宝物です。
信愛塾は、在日の親たちが子どもの教育の権利を求めることから始まった。愛情あふれる活動が発端です。人権の問題、日本に住む外国籍の人たちに真摯に向き合った活動をしてきている。その根本が変わらないがゆえ、そこを卒業した人たちが、時々元気な顔を見せに訪れてくれる。懐かしさとたくましさを感じる時です。そして、信愛塾につながっていることに悦びを覚えるときです。
火曜日のボランティアとして、限られた時間での交わりがありますがこの喜び、痛みに向きあわされていることに感謝です。どうすればいいか常に祈り、今あることに仕えていけたらと思います。子どもたちの上に幸あれ。主の恵みと祝福をお祈りします。