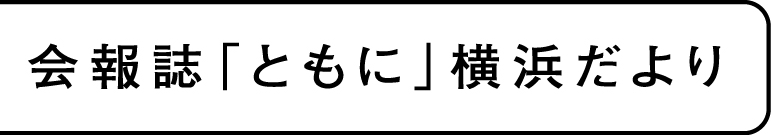23.12.20 No.74

- 自己紹介も兼ねて
-
「ともに」の読者の皆さま、こんにちは。今年の2月から信愛塾でボランティア・スタッフをしている閔庚大 (みん・きょんで) です。「ともに」には既にこれまで数回投稿していますが、今回改めて遅まきながら自己紹介も兼ねて私のバックグラウンドとそれを踏まえて昨今考えていることなど記載してみようかと思います。
私は、現在東京の大学院で社会学を専攻する学生で、信愛塾の過去から現在にかけて資料やインタビューなどを通じ、横浜において1970年代から現在にかけて時代ごとにいかなる状況が「民族差別」として問題化され、どのようにそうした状況の改善が求められたのかを検討しています。大学院進学前は、都内で会社員を3年ほどしていました。神奈川県相模原市で、日本人父親と私が生まれる前に日本国籍を取得した在日コリアン2世の母親の間に生まれ、大学時代は米国で過ごしましたが、それ以外人生のほとんどを、この信愛塾がある横浜市周辺の市町村で育ちました。そして横浜は、『横浜ベイスターズ』のファンである父親に連れられ、関内の野球場に試合を見にくるなど、小さい頃から思い出が多くある地でもあります。
勝手ながらもう少し私のバックグラウンドについて書こうと思います。私の父の家族は、この神奈川の湘南地域にルーツがあるそうです。明治時代末期に農家の次男として生まれた私の曽祖父は、丁度100年前の関東大震災の後、震災の影響で神奈川での生活が苦しく北海道の十勝地方に先に移住していた親戚を頼り「開拓民」として渡ったそうです。十勝では、いつ熊に襲われるかもわからない中、熊よけに鉄鍋をたたいて大きな音を出しながら、田畑を開墾したという話を聞いたことがあります。そうして生活を切り開いていった北海道で、私の祖父と父が生まれ、1970年代後半、父は大学進学を機に上京してきました。
他方、母親の家族は朝鮮半島と日本にルーツがあります。私の曽祖母は山形にルーツを持つ日本人で、1920年代前半、日本本土での厳しい生活を背景に、これもまた先に移住していた親戚を頼り当時日本の植民地であった朝鮮のソウル (当時の京城) に渡ったようです。そこで、私の曽祖父となる裕福な朝鮮人男性と出会い結ばれました。母方の家族は、終戦後も朝鮮半島に残留しました。しかし、1950年6月に始まった朝鮮戦争はかれらにとって大きな受難となり、そうした状況を背景に私の曽祖母は日本に戻ることを決意しそれに祖父も同行しました。その約10年後、私の母は東京で生まれました。
こうして家族のバックグラウンドをみると、私のルーツは戦前日本が北海道や朝鮮半島といった地域を侵略し、自身の領土を広げていく過程と密接に関わっているなと思います。そして、これら家族の歴史は少なからず現在の私を形作ってきたと思います。
そうした経験の一つとして、朝鮮半島にルーツを持つことに対する私と家族との認識の違いがありました。小さい頃から、私の母親は、私が朝鮮半島にルーツがあることを周りに言わないよう何度も繰り返し言っていました。実際、私の母親は友達を含め周りの人々に朝鮮半島にルーツがあったことをほとんど言ったことがないようです。そこからは、母親が生きてきた時代、そうした話をしたあとの影響を考えると簡単に言うことが出来なかった状況が思い浮かばれます。他方、私の場合は、小学校低学年時代に『冬のソナタ』などの韓国ドラマ、そして中学校に入ると『少女時代』『東方神起』などのK-POPといった韓国文化が日本で大衆化する時代に学生時代を過ごしました。そのため、母親が言うような朝鮮半島にルーツがあることを言ってはいけない状況がピンと来ず、何故ルーツを隠す必要があるのかと問う私と母親はこれまで度々対立してきました。
この問題は、単に母親との間だけで起きるわけではなく、父方の家族とも問題になってきました。幼い頃、毎年盆と正月は祖父母が住む北海道に遊びに行っていました。その際、何度か父や叔母などから「おじいちゃんには、韓国の話しちゃだめだよ」と言われたのがいまでも忘れられません。「開拓民」の子どもとして1920年代生まれの祖父は、彼自身が幼い頃から厳しい生活を送る中、誰がマジョリティでマイノリティであるかという固定的な概念を内面化せざるを得なかったということでしょうか。そうした状況の中、家族は皆大好きでしたが、なんとなくルーツをめぐる問題に関しては身方がいないと感じていました。
そしてこの感覚は、家族外での私の行動にも多かれ少なかれ影響を与えていたと思います。すなわち、私はルーツを隠さず生きていきたいと思っていた一方、家族は私にとって大切な存在なので極力かれらの思いも尊重したいと考え、二つの相反する意見の間で揺れ動いていました。大学3年生のとき、韓国の歴史の授業を履修しました。単に授業を履修するだけのことなのですが、私は韓国に関することを学ぶと言うことで家族にどう思われるかが気になり、しばらくの間悩み履修登録をする際には、手が震えていたことが思い出されます。日常生活を送るにあたって何か問題があるというわけではありせんが、心の中では常に縛り付けられるような苦しさがあったと思います。
話は大きく変わりますが、昨今のウクライナやパレスチナで起きていることをニュースなどで見ると心が痛みます。まず、誰かが暮らしていた土地を奪い自身のものにしようする行為から何が生み出されるのでしょうか。そして、問題が国対国という大きな単位で進められる中、そこで翻弄される個々の人々がいるということが捨象されていないかと思います。私の家族と私との関係のように、そこで翻弄された人々のトラウマは世代を超えて人々に影響を与えることもあるでしょう。とりあえず、現在の生活が苦しいから他人や後世の人々のことは考えず、一瞬楽になる方法を考えようとするのはあまりにも無責任な感じもします。
信愛塾が直面する状況のほんの一部しか私にはわかりませんが、毎週会う子どもたちの日々の生活にはなかなか厳しいものがあると度々実感させられます。そしてこの厳しさは単に今日昨日始まったものではないだろうと思います。大きな社会の動きの中、その歪みの影響を信愛塾に来る子どもたちは受けているのではないでしょうか。1978年10月に設立された信愛塾の基本方針には、その一部として「日本社会でたえず少数者として緊張を強いられている子らに、愛され、大切にされ、話を聞いてくれる、心の底から安心でき、喜ぶことのできる人間関係にはいらせる」とあります。色々な厳しさの中、子どもたちは紆余曲折を経験しつつも、信愛塾に毎週通いその日の出来事によっても様々ですが、思いっきりはしゃいで家に帰っていく日もたくさんあります。そうした様子を見ると、国や大人たちの取り決めなどに翻弄されつつも、信愛塾が一瞬でもそうした柵を忘れさせてくれる場になっているのではと考えます。信愛塾は今年で45周年を迎えますが、上記の45年前の基本方針は今でも生きているのだろうと思う昨今です。
- 無償の愛をください。―信愛塾の日常のスケッチー
-
信愛塾は南区中村町の一角にある。今日もマイバックやキャリーバックを持ったある母親が来る。そこに袋いっぱいの食料、日用品を入れ担いで帰る。3人の子どもを育てている母親は、子ども自身がお米を焚いてふりかけをかけて食べている、部活動をさせてあげたいが費用が苦しいなどの現状を伝え、「また来るね」と言って帰っていく。最近の物価高でどの家庭も打撃を受けているが、育ち盛りの子を育てているときはお釜のごはんが飛ぶようになくなっていく。現実は厳しく3件の家庭でガスが止められたと聞く。しかし、母親たちは明るい。
前期の成績が出て、中学3年生は進路について検討し始める。行きたい学校に入るのに自分の成績はどうか、高校見学をしたり自分の将来を考え始める。希望をかなえてもらいたいと個別相談や勉強のサポートを続ける。受験制度の中で基礎学力を身に付ける努力をする必要はあるが、外国籍の子どもたちにとっては二重、三重のハンディが伴なう。家庭環境を背景に落ち着いて勉強に取り組めないこと、日々の生活の困苦、そして語学力の壁などそれぞれが問題を抱えている。一人一人の歩みは、誰も同じではない。信愛塾の歩みは、一人一人の尊厳、人権と闘ってきた歴史である。そして、その厳しさと向き合うことで生きる力となってきた。どんなに泣いたか、どんなに悲しかったか、なんで暴れたか、なぜ心を閉ざしたかなどその痛みが取り除かれるようにと。そして、その取り組みは今も続いている。
なかなかなじめずじっくり椅子に座っていることができないK君は中国語しか話さずにいた。近くの公園で鬼ごっこをしているとその中に入ってきた。そして、一緒に逃げた。私が「鬼は誰」と聞くと続けて日本語で「だれ」と声を発した。そのことをJ子が「K君日本語喋った」と言った。次の週、1年生の国語の教科書の絵を一緒に見た。絵を見てお話ししながら尋ねると、動物の鳴き声をして答えてくれた。色を尋ねると赤、白、黒など日本語で答えてくれた。別の子の宿題をみてあげることになりK君と関わりが中断した時、小6年の女の子がわたしとK君のやり取りを見て同じことをしてくれた。自分を直ぐにそこに置くことが出来る彼女は自然に他者との関わりが身についている。彼女も自分の学力について学校から聞かされた時、その気持ちの整理ができず竹川さんに思いの限りをぶつけた。全てを聞いてくれた竹川さんに今度は彼女から笑顔で話しかけてきたという。
帰り際、K君に「気をつけて帰ってね」とバイバイすると暫くして帰って来て、また「気をつけて帰ってね」とバイバイすることが5,6回繰り返された。K君の気持ちはことばではなく態度と動作による表現であるため、こちらでよく受け止められないことがある。私はそのような時、気づいてあげれなくてごめんねとK君の頭をなでた。
また、M君は1,2年生の時に不十分な学習の期間があったため、ひらがなを書くこと、計算をすることが完全に身についていない。しかし、とてもやさしい子で、お手紙を書くときはM君の言った言葉を私がひらがなに書き、それを書き写してもらう。ある時、「先生、怖いお話聞いて」とストーリーテーリングを始めた。こんなにも日常会話がスムーズであるのにと、不思議に思う。また、運動会が行われた後、同じ学校の信愛塾のお友達に「旗をもって歩いていたね。」と、誇らしげに声を掛けた。仲間であることを言い現すことができる素晴らしさはかけがえもないものと思う。
生きていく上で必要な力、知恵、豊かさのありのままの状態を認め合う空間が信愛塾にある。一人一人の個性が花開くことの喜びと楽しみが詰まっている信愛塾は多くの人が日々の糧、日々の痛みを分かち合いながら、もがき続けている日常でもある。
- 【書評】「それは丘の上から始まった」後藤周著・加藤直樹編集 ころから
-

2023年9月1日は関東大震災が起こって100年目にあたる日だ。1923年9月1日、震災直後から広まっていった流言飛語によって多くの朝鮮人・中国人が警察や軍や自警団などによって虐殺された。ただこの本を読むとそう簡単な話でないことも分かってくる。軍の虐殺への関与は東京と横浜では明らかに違うし、警察の関与もワンパターンではない。警察署が破壊され機能を失った警察もあれば、警察が民衆と一体となって加害に及んだ記録もある。また血迷った民衆を説得できず、そのことが「警察も認めている」と流言を勢いづかせてしまった例まである。逆に地域の有力者の協力を得て朝鮮人を庇護した鶴見警察署の例などもあるという。
「それは丘の上から始まった」という書名は信愛塾にとっても極めて衝撃的である。何故なら「それ」というのはデマによるヘイトクライムであり、その「丘」とは信愛塾の目の前にある「平楽の丘」のことだからである。100年前、いま信愛塾がある近辺には木賃宿がたくさんあり、そこを宿としていた朝鮮人や中国人の労働者も犠牲になった可能性があるという。中村町は朝鮮人虐殺の舞台としてたびたび出てくるが、震災の起こった年に子どもたちが書いた「震災作文」などにも虐殺の様子が描かれている。信愛塾としてもこうした負の歴史をどう学び、活かし、次の世代にも正しく伝えていくのかが問われている。何故なら同じような歴史が二度と起こらないという保証はないからである。
本書を読むと、大地震や火災の恐怖に怯えた人々の姿や、その中で繰り広げられた朝鮮人・中国人に対する迫害、デマを信じて殺気立った民衆の姿などが不思議に思えるくらいリアルに伝わってくる。本書が圧倒的な説得力を持っているのは、個人の日記や手記、震災作文や行政でまとめた震災史、軍や警察の史料、当時の新聞、研究者の論文、当時の地名・地図など、実に様々な立場で書かれた史料を縦横に読み、考証重ね、事実が重なった部分のみを記述し、逆に、分からない部分は想像で埋めないという極めて実証主義的な態度が貫かれているからであろう。
時の権力に都合のいいような歴史解釈を行い、歴史の一部だけを都合よく継ぎはぎし、あったことをなかった事にしてしまう「歴史修正主義」(=虐殺否定論)が威力をふるっている。「政府内に事実関係を把握できる記録がない」などという松野官房長官談話などもその具体例であろう。巷に残された一冊の日記でも丁寧に読み、考証し、歴史の真実を明らかにしていこうとする著者の姿にこそ「歴史から学ぶ」ことの意味を知ることができる。
ちなみに著者の後藤周さんは長く横浜の中学校教員として実践的な教育を続けてこられた方で、「ヨコハマ・ハギハッキョ(夏期学校)」の運営にも最後までかかわり、また信愛塾の設立当初から今に至るまで信愛塾を支え続けている現役のメンバーでもある。
- 編集後記
-
今年最後のニュースとなりました。明るいニュースのない一年間でした。長引く戦争や紛争に私たちは戸惑い、自分は何ができるのかと、立ち止まり、問いかけ、考え込んでしまう日々でした。しかし、世界の出来事は私たちの生活に直結しています。決して他人事ではなく自分事として行動したいと思います。仕方ない、仕方なかったでは済まされません。戦車が轟音を立て、ミサイルが飛び交い、子どもたちが傷つき殺されていく・・・こんなことが許されるわけがありません。自分の居場所からの発信を続けましょう。時間はかかるかもしれませんが信愛塾の子どもたちも、育っていった青年たちも平和を作り出す使者として成長してほしいと願います。憎しみのあるところに愛を、争うのあるところに平和を、そして絶望のあるところに希望を、みんなで作り出したいと思います。いつも信愛塾に心を寄せてくださる皆様に「感謝」の気持ちをお伝えします。